【空き家所有者向け】長崎の空き家を譲渡して負担を減らす方法
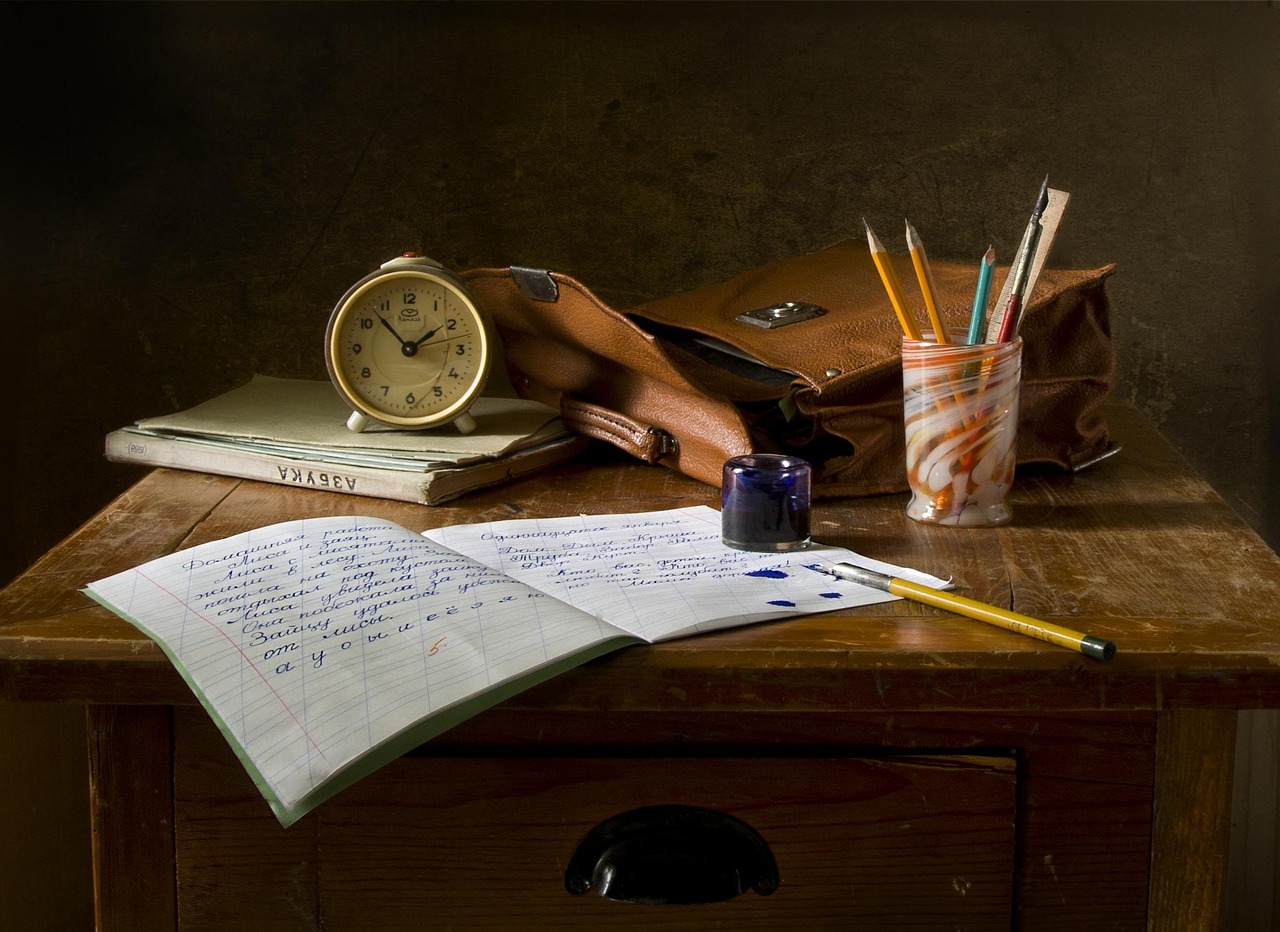
長崎で空き家を所有している方の中には、「手元に残すか、手放すか悩んでいる」「手放したいけど買い手がつかない」とお悩みの方もいらっしゃると思います。特に思い入れの強い空き家であれば、その扱いに迷われるでしょう。
そんなとき考えていただきたいのが、空き家を譲渡するという選択肢です。譲渡とは、売却のように利益を目的とせず、管理できない空き家を再活用してくれる人や団体へ引き継ぐ方法です。
この記事では、長崎で空き家を所有している方に向けて、空き家を譲渡する方法を詳しく解説します。空き家を放置するリスクから、注意点や税金の取り扱い、実際の再生事例まで紹介します。空き家の行き先に悩む方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
空き家を放置すると発生する3つのリスク
「使っていない家だけど、放っておいても問題ない」と考えていませんか?空き家を放置すると、所有者の責任として避けられないリスクが発生します。主なリスクは、以下の3点です。
<税金負担>
空き家を所有している限り、たとえ居住していなくても固定資産税や都市計画税の支払い義務が発生します。
通常、住宅が建っている土地は固定資産税が最大6分の1に軽減されますが、倒壊の危険があるなどの「特定空き家」に指定されると、この軽減措置が解除されてしまいます。2023年12月に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(改正空き家特措法)により、その前の段階である「管理不全空き家」に指定された場合でも解除の対象となりました。
管理されていない空き家は、税金の負担が重くなるのです。
<倒壊の恐れ>
老朽化した空き家では、屋根の崩落や外壁の剥離、雨漏りによる腐食などが進行し、倒壊するリスクが高まります。実際に、台風や地震で倒壊する事例をニュースで目にされたことがあるでしょう。
市町村は「空家等対策特別措置法」に基づき、危険と判断された建物に修繕・撤去の勧告や命令を出すことができます。従わない場合は行政代執行で解体され、費用が所有者に請求されるケースもあります。

草が生えすぎて、室内に入り込んでいます。
<賠償責任>
放置された空き家は、ゴミが溜まったり雑草が繁茂したりすると、害虫の発生や景観悪化を招く要因です。建物の一部が落下する、倒壊するなどして人や車を傷つける可能性も否定できません。空き家を放置すると、近隣にまで迷惑をかける恐れがあるのです。
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)により、建物の所有者は第三者に与えた損害について無過失責任を負います。つまり、所有者に過失がなくても、建物の不備による被害について賠償責任が生じます。
このように、空き家を持ち続けて放置すると、経済的にも法的にもリスクがあるのです。
譲渡とは?売却との違い
放置するとリスクのある空き家を手放すと考えたとき、まず「売却」することが思い浮かぶでしょう。しかし、老朽化した建物や立地条件が悪い物件は、買い手がつきにくいのが現実です。そこで注目されるのが、「譲渡」という方法です。
売却は、所有者が金銭を受け取る行為です。買い手を探し、契約・決済を行い、市場価値に基づいた金額を受け取ります。
一方、譲渡は無償または極めて低い金額で空き家を引き渡す方法です。お金を得ることではなく、適切に管理・再生してくれる人に託すことが目的です。所有者は大きな金銭を受け取ることはできませんが、処分に困る空き家を手放すことで、さまざまなリスクから解放されます。
地域にもよりますが、安価な戸建を探している移住希望者や投資家のニーズが存在します。譲渡によって、リスクのある空き家を地域資源に変えることができるのです。特に長崎は、地形の制約があり宅地開発できるエリアが限られるため、空き家は移住希望者や投資家にとって魅力的な選択肢となり得ます。
譲渡は単なる引き渡しではなく、「誰に、どのような思い」で託すかを考える行為でもあります。思い出の詰まった家を解体するのではなく、次の世代に生かしてもらう視点を持つことで、譲渡は「手放す」から「地域へ託す」ことへと意味を変えます。
長崎で空き家を譲渡する3つの方法
「空き家を譲渡したいけれど、どうすれば良いのだろう?」と疑問に思われる方も多いと思います。そこで、長崎で選べる3つのルートを紹介します。
<「空き家バンク」を活用する>
もっとも安心なのが、自治体が運営する「空き家バンク」制度です。長崎でも、長崎市・諫早市・島原市から島しょ部まで、各地で導入されています。
空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい所有者と、住みたい・活用したい人をマッチングする仕組みです。空き家の所有者が自治体に登録を申告し、自治体による現地確認を受け、写真や所在地などの情報をウェブサイトに掲載します。売買だけでなく、無償譲渡の登録も可能で、登録料や仲介手数料もかかりません。
マッチングに時間がかかる場合もありますが、公的な仕組みのため、安心して利用できるのもメリットです。全国どこからでもウェブサイトを閲覧できるため、空き家を探す移住希望者や投資家の多くは、まず空き家バンクをチェックします。
空き家バンクは、長崎で空き家を譲渡する際にぜひとも活用したい手段です。
参考:長崎市移住・定住応援公式サイトながさき人になろう「空き家・空き地情報バンク(空き家バンク)」
<不動産会社に依頼する>
譲渡に対応する不動産会社はほぼ見られませんが、なかには無償譲渡に対応している会社も存在します。不動産会社を頼ることができれば、空き家再生に積極的な投資家やリノベーション会社とつながるチャンスがあります。
不動産会社に相談する際は、物件の状態や登記上の名義、相続関係を整理しておくとスムーズです。
当社は長崎市を拠点とし、空き家を住宅として再生しています。空き家を手放したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
<NPO・個人投資家に引き継ぐ>
地域で空き家再生に取り組むNPO法人やまちづくり団体に引き継ぐ選択肢もあります。このような団体の目的は、空き家をリノベーションして住まいやコミュニティ拠点に再生し、地域資源として活かすことです。
また、空き家のリノベーションに投資する個人投資家も存在します。
譲渡は、誰に託すかが重要です。譲渡を考えている空き家には、何かしら思い出や思い入れがある方が多いでしょう。地域とつながりを持つ団体や事業者に託すことで、家が再び息を吹き返します。
譲渡の注意点と税金の取り扱い
譲渡にはさまざまなメリットがありますが、いくつかの注意点も存在します。ここでは、大きく3つの注意点を解説します。
<登記を確認しておく>
空き家を譲渡する際は、登記上の所有者を明確にする必要があります。もし、相続した空き家で相続登記をしていない場合、譲渡ができません。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したら、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の適用対象となります。
また、複数人で共有している空き家を譲渡するには、全員の同意が必要です。自分の持分だけ譲渡することは可能ですが複雑になるため、専門家へ相談することをおすすめします。
さらに、譲渡する際は所有権の移転登記が必要です。所有者権の移転登記をすることで、その不動産の正当な所有者を法的に明確にし、第三者に対して所有権を主張できるようになります。
固定資産税は登記上の所有者に課税されます。そのため、所有権移転登記を行わなければ、譲渡後も税金を支払い続けなければなりません。
<個人間の取り引きによるリスクがある>
空き家の譲渡においては、不動産会社を通さずに個人間での取り引きとなるケースが大半を占めます。空き家バンクを活用する場合も同様です。マッチングを手助けしてもらっても、最終的な契約手続きは当事者同士ですることになります。
所有権の移転登記や契約の手続きまで、すべて自分で行わなければなりません。仲介業者が入らない分、スピーディーに話が進められる面がある一方で、労力がかかりす。不動産取り引きには専門的な知識を要するため、専門家不在で進めるとトラブルが発生しやすいです。
<譲渡後のトラブルを未然に防ぐ>
空き家には、譲渡が済んだ後にトラブルとなるリスクが潜んでいます。見えない部分の腐食が見つかるといった重大な欠陥があった場合、契約不適合責任を問われる可能性もあります。譲渡後のトラブルを防ぐには、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。近隣や境界の問題なども含めて、事前の調査と告知を怠らないようにしましょう。
譲渡後に、「家を壊されてしまった」「想定していた用途と違った」といったトラブルも起こりかねません。トラブルを防ぎ、譲渡人と譲受人の双方が気持ち良く取り引きするために、契約書を作成して譲渡条件を明記することが重要です。
上記の3点が、空き家を譲渡するときの主な注意点です。加えて、税金の取り扱いについても確認しておきましょう。
空き家を譲渡する場合、方法や条件によって税金が発生する可能性があります。
まずチェックしておきたいのは、譲渡所得税です。譲渡所得税は、不動産を売却して利益(譲渡所得)を得た際に課税されます。譲渡所得は「不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)」で算出され、無償譲渡や著しく低い価格での譲渡であれば、譲渡所得はゼロまたはマイナスとなります。そのため、空き家の譲渡において、譲渡所得税は発生しない場合がほとんどです。
なお、相続で取得した空き家を売却・譲渡する場合、「被相続人居住用財産の譲渡特例(3,000万円控除)」が適用できるケースもあります。
注意しなければならないのは、贈与税です。個人に対して無償で空き家を譲渡すると、譲受人に贈与税が課税される可能性があります。年間110万円までの譲渡であれば贈与税は発生しませんが、不動産の評価額がそれを超える場合には、譲受人が贈与税を納めなければなりません。
税金の取り扱いは複雑で、ケースによって異なるため、専門家への相談をおすすめします。
実際の譲渡事例
最後に、相続された空き家を投資家が再生した事例を紹介します。
Aさんは、古い木造住宅を相続で受け継ぎました。しかし、Aさん自身は実家を離れて遠方に住んでいたため、管理が不十分になっていました。屋根が痛み、内部も老朽化して、草木が伸びて景観も悪化している状態です。年に数回、除草などのために遠方から訪れる交通費も負担となっていました。
老朽化した空き家には買い手がつかず、解体するにも200万円ほどかかるため踏み出せずにいました。その間、維持コストが重くのしかかり続けます。
そんな中、売却ではなく譲渡するという方法を知り、譲受人を探したところ、投資家のBさんとつながりました。Bさんは、譲り受けた空き家をリノベーションし、住宅として再生。賃貸に出して、家賃収入を得ています。
一方、Aさんは管理負担や税金の支払いから解放されました。負担になってしまっていた大切な実家が、新たな住民に使ってもらえる家に生まれ変わったのです。防犯上のリスクが軽減され、景観も改善されたため、地域住民にとっても喜ばしいことでした。
所有者は負担から解放され、投資家や地域にとっては新しい価値が生まれたのです。
まとめ:空き家を手放すことは「地域に託す」選択肢
思い出が詰まった空き家、思い入れのある空き家を手放すことを躊躇する方もいらっしゃると思います。一方で、管理にかかる時間やお金を負担に感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、空き家は誰かに託すことで息を吹き返すことができます。空き家を譲渡することは、自らが管理や税金の負担から解放されるだけでなく、家が再生されて地域の資産となったり、伝統的な古民家が地域に受け継がれたりと、持続可能なまちづくりにつながる行動です。
空き家を手放すことは、「地域に託す」という選択肢です。空き家の扱いに悩んでいる方が、「譲渡」に関心を持っていただけたら幸いです。当社は長崎市を拠点に、空き家を次世代へ引き継ぐ事業を行っています。空き家を手放すことをお考えの方は、お気軽にご相談ください。
