【長崎の空き家所有者へ】譲渡で管理負担を減らす方法とは?
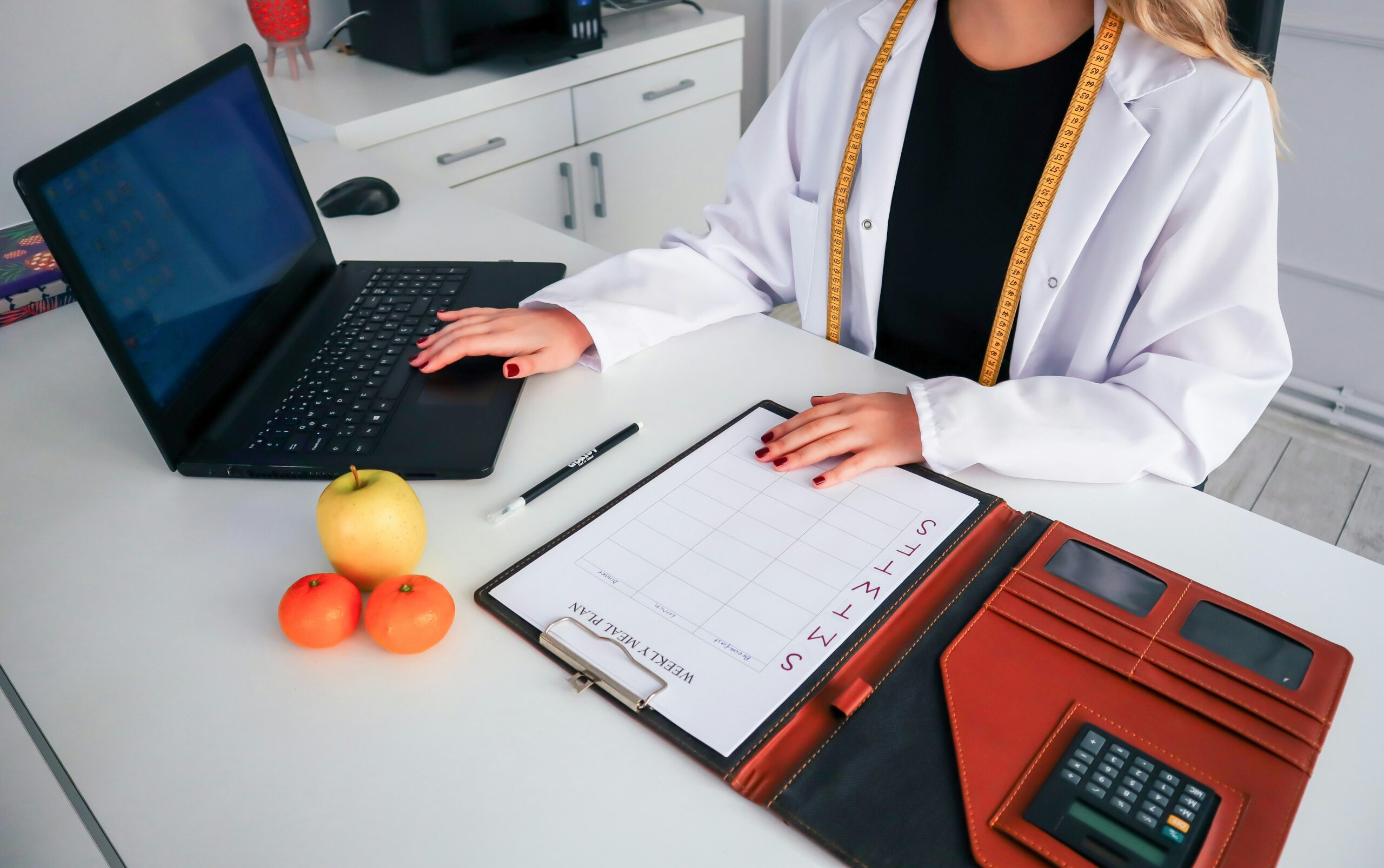
長崎県は、全国でも空き家率が高い地域です。総務省統計局の「令和5年住宅・土地統計調査結果」によると、総住宅数に対して、賃貸や売却用、別荘などを除く空き家率は、9.9%となっています。全国平均の5.9%よりも4%も高い数値です。
相続や転居により、使わなくなった家をそのまま持ち続ける人が増えています。空き家は人が住んでいなくても固定資産税や管理の負担が重くのしかかります。解体しようにも費用がかかるため、「どう手放すか」悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで注目したいのが、「譲渡」という方法です。売却のようにまとまったお金が入るわけではありませんが、管理や税金から解放され、誰かに使ってもらえる可能性が広がります。
この記事では、長崎で空き家を所有する方に向けて、「譲渡」という選択肢の実態とメリット、具体的な方法、注意点を解説します。
空き家を「譲渡」するとは?
「譲渡」とは、空き家を売却するのではなく、無償または低価格で第三者に引き渡す方法です。「処分に困る空き家」を手放すことで、所有者は空き家の管理や税金負担から解放されます。
通常の売買では市場価格で売ることを目指しますが、老朽化した空き家や需要の乏しい立地の空き家は買い手が見つからないことも珍しくありません。一方で、長崎では移住希望者や投資家が安価な戸建を探しているため、ニーズは存在しています。
譲渡は、処分に困る空き家を手放したい所有者と、安価で空き家がほしい移住希望者や投資家のニーズを結びつけるのです。
長崎は地形の制約もあり宅地開発が難しいエリアが多いため、古い戸建住宅が移住希望者や空き家再生投資家にとって魅力的な選択肢です。所有者が負担に感じている空き家が、別の人にとってはチャンスとなり得ます。
所有者にとっての譲渡のメリット
空き家を譲渡することで所有者が得られるメリットは、大きく4つあります。
<固定資産税・管理負担からの解放>
空き家を所有し続けることによる大きな負担は、固定資産税です。誰も住んでいなくても、固定資産税は毎年必ず支払わなければなりません。
また、空き家の管理も必要です。空き家の近くに住んでいる方であればまだしも、遠方に住んでいる場合、空き家の管理は想像以上に苦労します。庭の草木は放置すれば伸び放題となり、近隣に迷惑をかけることになります。多くの所有者が年に数回、県外から長崎まで帰省して草刈りを行っているのが実情です。
建物そのものの劣化も進みます。人が住まない家は急速に傷み、雨漏りやシロアリ被害、窓ガラスの破損などが発生します。修繕を怠れると建物の倒壊リスクが高まり、近隣住民にまで被害が及ぶ可能性も否定できません。
空き家を譲渡すれば、このような金銭的な負担、精神的な負担から一気に解放されます。
<解体費用の節約>
空き家を処分する際、多くの所有者が直面する問題が解体費用です。解体費用の相場は、一般的な木造住宅で4万〜5万円/坪、鉄骨造で6万〜7万円/坪、鉄筋コンクリート造で7万〜8万円/坪ほどです。総額で200万円を超えることもあります。
長崎は坂が多く、重機が入りにくい場所も多くあります。そのような立地では作業に時間を要し、費用が高くなりがちです。古い建物にはアスベストが使用されている可能性もあり、その処理には専門的な対応と追加費用が必要です。
また固定資産税には「固定資産税等の住宅用地特例」があり、住宅が建っていると軽減措置を受けられますが、空き家を解体して更地にすると軽減措置がなくなります。よって、負担が増えてしまうのです。加えて、更地にしたからといって必ずしも売却できるわけではなく、結局は税金を払い続けることになるケースも多いのです。
譲渡という選択肢を選べば、こうした高額な解体費用を支払うことなく、空き家を手放すことができます。
<地域貢献という価値>
空き家を誰かに譲渡することは、単に自分の負担を減らすだけでなく、地域社会への貢献にもつながります。
長崎では、若者の県外流出や人口減少によって、空き家の増加が顕著です。放置された空き家は景観を損ね、防犯面でも問題となり、地域全体の価値を下げる要因となります。空き家が再生されて誰かが住むようになれば、このような問題を解決できます。
長崎は観光都市としての側面を持っているため、空き家が民泊やゲストハウスに生まれ変われば、観光資源になる可能性も秘めているのです。
長年住み慣れた実家や、先祖代々受け継いできた家を手放すのに迷いがある方も、ただ解体してしまうよりは「地域のためになる、誰かの役に立つ」ほうが精神的にも納得感を得られるのではないでしょうか。
長崎で空き家を譲渡する方法
「空き家を譲渡するメリットはわかったけれど、どのように譲渡したら良いの?」と気になりますよね。ここでは、代表的な4つの方法を紹介します。
1.自治体の「空き家バンク」に登録
長崎市をはじめ、地方自治体では「空き家バンク」という仕組みを設けています。空き家バンクは、空き家を「貸したい・売りたい」所有者と、「借りたい・買いたい」利用希望者をマッチングするサービスです。
自治体が運営しているため、初めての方でも安心して利用できます。マッチングにあたって、仲介手数料もかかりません。
空き家を探す移住希望者の多くは、まず空き家バンクをチェックします。ウェブサイトから誰でも長崎の空き家情報をチェックできるため、登録すれば、全国にいる長崎への移住希望者に情報を届けられます。
利用のおおまかな流れは、以下のとおりです。
①自治体へ、物件の登録希望を申し出る
②登録要件を満たすかどうか、自治体の担当者による現地確認を受ける
③登録申込書を提出する
④情報登録などの手続きを行う
⑤内覧会に参加し、購入希望者の対応をする
⑥当事者同士で交渉・契約する
空き家の譲渡をお考えの方は、ぜひ「空き家バンク」を活用してみてください。
参考:長崎市移住・定住応援公式サイトながさき人になろう「空き家・空き地情報バンク(空き家バンク)」
2.不動産会社に相談
地元の不動産会社に相談することも有効な方法です。不動産会社というと売買のイメージが強いかもしれませんが、無償譲渡に対応している会社も存在します。
長崎で空き家再生に力を入れている不動産会社であれば、独自のネットワークを持っており、物件を必要としている人や団体とのマッチングしてもらえる可能性があります。
会社によって得意分野や持っているネットワークが異なるため、一社だけでなく複数社に声をかけてみても良いかもしれません。
3.NPOや地域団体に譲渡
地域活性化を目的に活動しているNPOや自治会に譲渡するのもひとつの選択肢です。
たとえば、空き家をコミュニティ拠点や子育て支援施設、シェアハウスとして再生する事例が考えられます。NPOや地域団体は営利目的ではないため、地域のために空き家を活用してもらえるという安心感があります。
NPOや地域団体を探す際には、各自治体の地域振興課やまちづくり推進課などに問い合わせてみると良いでしょう。
4.個人投資家へ直接譲渡
地方の戸建物件への投資に関心を持つ個人投資家が存在します。個人投資家は、空き家を安く取得してリフォームし、賃貸物件や民泊として運用することを考えています。
SNSやマッチングサイト、セミナーを通じてこのような個人投資家と出会い、直接交渉するのもひとつの方法です。間に仲介業者が入らない分、スピーディーに話が進められるというメリットがあります。
一方、個人間での取引にはリスクも伴います。契約内容をしっかりと確認し、特に所有権の移転登記など法的な手続きを適切に行うことが重要です。
空き家を譲渡する際の注意点
空き家の譲渡には、大きなメリットがありますが、同時に注意しておくべき点がいくつかあります。
<登記の名義変更が必須>
空き家を譲渡する際に最も重要なのが、所有権移転登記です。
所有権移転登記とは、不動産の所有権が現在の所有者から別の所有者に移った際に、その事実を登記簿に記載する手続きです。この登記を行うことで、誰がその不動産の正当な所有者であるかを法的に明確にし、第三者に対して所有権を主張できるようになります。すなわち、空き家の名義を変更する手続きということです。
固定資産税は登記上の所有者に課税されるため、所有権移転登記を行わなければ、譲渡後も税金を支払い続けなければなりません。
また、相続によって取得した空き家の場合、まず相続登記を行わなければ譲渡できません。もし相続登記が済んでいない場合は、相続登記の手続きを優先しましょう。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したら、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の適用対象となります。
<建物状態による制約>
譲渡を希望しても、建物の状態によっては引き受け手が見つからないケースもあることを認識しておきましょう。倒壊の危険性が高い建物や大規模な修繕が必要な物件は、無償であっても引き受けを躊躇される可能性が高いです。
なぜなら、引き受ける側にとって、譲渡後のリフォーム費用や解体費用が負担となるためです。こういったケースでは、所有者側で最低限の修繕を行ってから譲渡するか、解体後の更地として譲渡することも検討する必要があります。ただし、解体には前述のとおり高額な費用がかかるため、費用対効果をよく考える必要があります。
また、再建築不可の物件にも注意が必要です。建築基準法上の接道義務を満たしていない土地では、建物を解体すると新たに建物を建てられません。
<税金の確認が必要>
空き家を譲渡する際には、税金に関する確認も必要です。譲渡の方法や条件によっては、譲渡所得税や贈与税が発生する場合があるため、事前に税理士などに相談することをおすすめします。
譲渡所得税は、不動産を売却して利益(譲渡所得)を得た際に課税される税金です。譲渡所得は、不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)で算出されます。無償譲渡や著しく低い価格での譲渡であれば、譲渡所得はゼロまたはマイナスとなるため、譲渡所得税は発生しない場合が多いでしょう。
一方、注意が必要なのは贈与税です。個人に対して無償で不動産を譲渡すると、受け取る側に贈与税が課税される可能性があります。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、不動産の評価額がそれを超える場合には、受贈者が贈与税を納めなければなりません。
<契約条件の調整>
譲渡を進める際には、契約条件を明確にすることが非常に重要です。
場合によっては「更地にしてから譲渡」という条件を譲渡先が求めるケースもあり、解体費用を所有者が負担しなければなりません。前述のとおり、解体の際は注意点が多いため、慎重に検討しましょう。
空き家の譲渡が進みやすいケース
空き家の中でも、譲渡が進めやすいケースが存在します。
やはり重要なのは立地条件です。長崎市内でも、市街地に近い場所や、バス停から徒歩圏内にある物件は、引き受け手が見つかりやすい傾向があります。
建物の状態も重要なポイントです。小規模であっても、リフォーム次第で住める状態であれば、引き受け手は見つかりやすくなります。
建物に特徴や魅力があるのも加点要素です。いろりがある、庭が広い、眺望が良いなど、長崎ならではの歴史的価値や、観光資源に結びつきそうな要素があれば、大きな強みとなります。
このような空き家はカフェや民泊としての活用できる可能性があり、需要の幅が広がります。
まとめ
長崎は全国的に見て空き家率が高い地域です。空き家は、所有し続けると税金や管理負担が重くのしかかります。そんな負担から解放される手段のひとつが、「譲渡」という方法です。
空き家の引き受け手を探してくれたり、自ら引き受け手になったりしてくれる自治体や不動産会社、NPO、個人投資家とつながることが、「負担から資産」に変えるきっかけになります。
どうしても負担が生まれてしまう空き家が、地域の資産に生まれ変わる可能性は十分にあります。長崎に空き家を所有している方は、ぜひ一度「譲渡」という道も検討してみてください。
